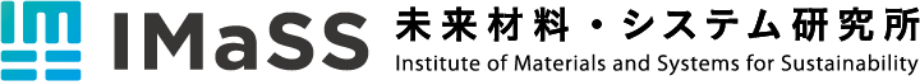Research
Glossary
用語解説
あ 行
-
アニオン交換膜(AEM)
正に帯電した固定基(通常は第四級アンモニウム基など)を持ち、OH-などの陰イオンのみを選択的に透過させる高分子膜。 《使用例》1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進 燃料電池、CO2回収など応用デバイス開発へ重要な一歩…
-
異方性磁気抵抗
(Anisotropic Magnetoresistance: AMR)強磁性体の磁化の向きと電流方向のなす角度に依存して、電気抵抗が変化する現象。電流方向と磁化方向が平行の時が、電流方向と磁化方向が垂直の時と比べて電気抵抗が大きくなる。磁…
-
RDE(アールディーイー)
ローテーティングデトネーションエンジン(=Rotating Detonation Engine)。デトネーションを二重円筒内の底部に周回(回転)し続けるように発生させることで高圧ガスを発生させ、それを円筒の軸方向に噴射し、その反動としての推…
か 行
-
カチオン交換膜(CEM)
負に帯電した固定基(通常はスルホン酸基など)を持ち、H+などの陽イオンのみを選択的に透過させる高分子膜。 《使用例》1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進 燃料電池、CO2回収など応用デバイス開発へ重要な一歩…
-
過電圧
理論的な電圧に対して、実際に反応を進行させるために必要となる追加の電圧。過電圧が高いほど、エネルギー損失が大きくなる。 《使用例》1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進 燃料電池、CO2回収など応用デバイス開発へ重要な一歩…
-
蛍光板
電子が当たると発光する塗料の塗ってあるTEM像、回折図形等を直接観察するためのアナログな道具。
-
結晶欠陥
結晶格子の乱れ。原子空孔や格子間原子、不純物原子、転位、析出物など。結晶欠陥自身は半導体デバイス特性を低下させる要因となるが、デバイス活性領域外に適切に形成された結晶欠陥は活性領域の金属不純物を捕獲する(ゲッタリング)など、半導体デバイス特…
-
格子の振動(フォノン:結晶中の波)
結晶格子は、規則正しく原子が整列し結合することでエネルギー的に安定化している。エネルギーが加わり安定構造から少しずれた時に、安定構造を中心として起こる構造変化の振動。 《使用例》マルチフェロイック結晶の分極を10兆分の1秒の光で制御 ~強…
-
こうのとり
JAXAが開発した、地上から荷物を持って運ぶ宇宙ステーションへの補給機。ロケットでまず打ち上げてもらって、宇宙空間を宇宙ステーションまで自力で飛行し、ドッキングして、荷物を降ろし、要らない荷物を積んで、宇宙ステーションから離脱し、最後大気圏…
-
交流インピーダンス測定(EIS)
電極系に微小な交流電圧を印加し、電流応答との周波数依存性から、電気化学反応の抵抗要素や緩和時間を解析する手法。反応の速度論的解析や界面抵抗の評価に用いられる。 《使用例》1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進 燃料電池、CO2回収な…
-
合胞体(syncytium)
2個以上の核を持つ細胞。単核細胞の融合、あるいは細胞分裂の不全で生じる。デンキウナギ発電細胞の他には骨格筋、哺乳類の胎盤、ウイルス感染細胞の細胞変性効果で見られる。 《使用例》 デンキウナギの発電器官に未分化様の細胞を発見~発電細胞の“…
さ 行
-
CIS(シーアイエス)
CMOSイメージセンサーを指し、カメラの撮像素子のこと。スマートフォン、デジタルカメラ、監視カメラ、産業用センサーなど、多様な用途で用いられている。 《使用例》半導体の製造プロセスを“一気通貫”で最適化!~AI活用により企業の壁を越えスピ…
-
重量規格化電流密度
触媒の質量1gあたりの単位面積(通常1cm2)における電流密度(mA/cm2/g)を指す。触媒の活性を比較するための重要な指標であり、高効率な触媒ほどこの値が大きくなる。 《使用例》1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進 燃料電池、…
-
人工強磁性細線
組成の異なる強磁性金属同士の層厚がnmオーダーで多層構造になった細線のこと。1980年代頃から研究が始まった「人工格子」(各層の厚さを原子層単位で制御して積層した人工的多層膜のこと)になぞらえて「人工強磁性細線」と名付けた。 《使用例》層…
-
スピントロニクス
電子の持つスピンの自由度を利用することで、従来のエレクトロニクスに無い新機能・高性能素子の実現を目指す研究開発分野。 《使用例》層厚を制御した人工強磁性細線の作製に成功 ~ 人工強磁性細線を利用した大容量メモリや磁気センサ開発へ道筋 ~…
-
セカンド・ウィーン効果
強電場中において、溶液中の電解質が通常よりも高い割合で電離する現象。バイポーラー膜界面での水解離反応の重要な理論的根拠となっている。 《使用例》1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進 燃料電池、CO2回収など応用デバイス開発へ重要な…
-
前駆細胞(progenitor cell)
細胞の形態や性質が専門化(分化)する前の状態。必要とされるまで休眠状態にあり、分化に必要な遺伝子の働きで活性化する場合もある。 《使用例》 デンキウナギの発電器官に未分化様の細胞を発見~発電細胞の“できかた”解明への第一歩~…
た 行
-
デジタルツイン
コンピュータ内に構築された実際の工程のモデル。 《使用例》半導体の製造プロセスを“一気通貫”で最適化! ~AI活用により企業の壁を越えスピーディな性能改善に貢献~…
-
電子顕微鏡(種類)
・透過型電子顕微鏡(TEM)…対象物に電子を透過させて観察する。対象物は厚さ0.1μm以下のもの。 ・走査型電子顕微鏡(SEM)…対象物の上に電子線を走らせ(scan)、対象物から出る二次電子の情報から像を描き出す。…
-
電子顕微鏡(倍率)
光学顕微鏡で見えるものは、光の波長程度、すなわち約0.2μ(マイクロ)m(=200n(ナノ)m)ほどだが、光の波長の10万分の1以下の電子線を使った電子顕微鏡を用いると、光学顕微鏡の約1,000倍もの分解能があり、0.1nmの原子も見える。…
-
電子顕微鏡(しくみ)
電子レンズに電流を流すと電磁石になる性質を利用して電子線を曲げ、最終的に投影スクリーンに映し出されるしくみ。電子線が顕微鏡内の長い距離を進むよう、顕微鏡内部は真空になっている。
-
電子線パルスを用いた最新の構造測定装置
電子は、波としての性質を持つため、結晶にあたると、結晶中の原子による散乱波が干渉を起こし、回折像が観測される。この回折像を解析することで、結晶構造の情報を得ることが出来る。光励起による構造変化の様子を、試料を励起するパルス光と時間的同期のと…
な 行
-
Na+/K+-ATPase
細胞膜上に存在し、イオンを運搬する性質をもったタンパク質(イオンポンプ)のひとつ。エネルギーを消費してナトリウムイオン(Na+)を細胞の内から外へ、カリウムイオン(K+)を外から内に運搬する。同時に運搬するイオンは3個のNa+と2個のK+で…
-
ナノシート
原子1層、数層からなる物質。代表的な物質として、グラフェン、六方晶BN、遷移金属カルコゲナイド(MoS2、WS2など)がある。 《使用例》1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進 燃料電池、CO2回収など応用デバイス開発へ重要な一歩…
-
ナノメートルのスケール
人が識別できるサイズはmm単位、1mm(ミリ)の1,000分の1が1μ(マイクロ)m(たんぱく質や細胞の大きさがこの領域)で、さらにその1, 000分の1が1nm(ナノ)。すなわち、1mmの100万分の1となる。つまり、ナノメートルサイズの…
-
二浴電析法
2種類の電解質溶液を利用して電析する手法。異なる電解質溶液で電析を行い、異なる物質を積層させることができる技術。一方で、積層させる電極などを異なる電解質溶液間で物理的に移動させる必要がある。 《使用例》層厚を制御した人工強磁性細線の作製に…
は 行
-
発電細胞(electrocyte)
発電生物で放電を行う細胞。運動神経からの入力によって生成した膜電位を、体外へと放出する。一般には筋肉が変化して発電細胞になると考えられているが、明確な実験的検証はまだない。 《使用例》 デンキウナギの発電器官に未分化様の細胞を発見~発電…
-
発電生物(electric organisms)
体外への放電を攻撃や防御、知覚やコミュニケーションに活用できる生き物の総称。脊椎動物では魚類だけで報告があり、デンキウナギ、デンキナマズ、シビレエイなどが一般的な知名度をもつ。 《使用例》 デンキウナギの発電器官に未分化様の細胞を発見~…
-
バイポーラー膜(BPM)
カチオン交換膜とアニオン交換膜という、イオン選択性の異なる2種類の膜を積層して構成される複合膜。両膜の界面では、水分子が水素イオン(H+)と水酸化物イオン(OH-)に解離する「水解離反応(Water Dissociation…
-
パルス電析法
時間とともに電流(または電圧)を変化させる電析法で、パルス波形を用いた手法。析出物の表面形態、結晶粒径、構造を制御できる手法である。直流電流(または直流電圧)に比べて拡散層の厚さを薄くでき、高いパルス電流密度で電析することができる。 《使…
-
光パルス
カメラのフラッシュランプのように、極短時間だけ発生した光。 《使用例》マルチフェロイック結晶の分極を10兆分の1秒の光で制御 ~ 強誘電・磁気メモリーデバイスの超高速操作が室温で可能に~…
-
分極
固体中で、正の電荷と負の電荷が空間的に分離することで、反転対称性を破った状態。その大きさや向きを保持し、外部電場に応じて切り替わることで、情報を記録するメモリとして応用されている。 《使用例》マルチフェロイック結晶の分極を10兆分の1秒の…
-
PDE(ピーディーイー)
パルスデトネーションエンジン(=Pulse Detonation Engine)。デトネーションを発生させることで高圧ガスを発生させ、それを間欠的(パルス状)に噴射し、その反動として推力を得る装置。 《使用例》ロケットエンジンも革新的な軽…